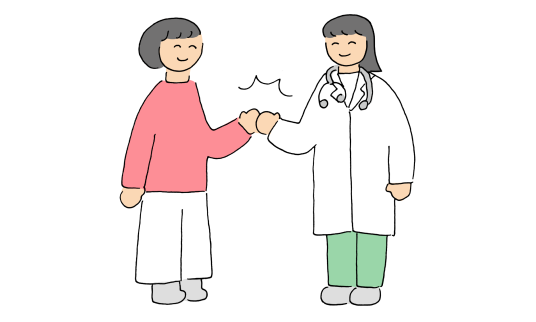コラム
不妊症・不育症について

不妊症について
不妊症とは
日本では、妊娠を望む健康な男女が、避妊をしないで性交しているにもかかわらず、妊娠しない状態が1年以上続くことを「不妊」といいます。なお、妊娠を希望し、かつ、子どもを授かるために医学的な治療が必要とされる場合は、妊娠をしない期間が1年未満であっても「不妊症」と診断されます。
不妊症の主な原因
不妊の原因は、女性側に原因があるもの(女性因子)、男性側に原因があるもの(男性因子)、検査を行っても原因が特定できない場合(原因不明不妊)に大きく分けられます。不妊に至る原因は、男女のどちらか一方にある場合だけでなく、男女両方にある場合もあります。なお、不妊の原因の男女比は、ほぼ同数と言われています。
| 女性因子 |
| 排卵に問題がある(排卵因子(内分泌因子)) |
卵子が育たない、育っても排出できないなど、排卵が正常に行われないために、引き起こされる不妊を「排卵因子」の不妊といいます。排卵には、さまざまな性ホルモンの分泌(内分泌)が関与しているたため、排卵因子を(内分泌因子)とも呼ばれます。
【排卵因子による不妊症の主な原因】
- 視床下部・下垂体性排卵障害
- 高プラクチン血症
- 多嚢胞性卵巣症候群
- 黄体機能不全
- 甲状腺疾患
| 卵管に問題がある(卵管因子) |
卵子と精子の通り道である卵管が炎症などによりふさがっていたり、狭くなっていたりするなど卵管に問題があるために起こる不妊を「卵管因子」の不妊といいます。
クラミジアに感染したことがある場合、気が付かないうちに卵管炎や骨盤腹膜炎といった炎症が起こり、卵管がふさがることがあります。また、子宮内膜症によって、卵管周囲の癒着がおこり、卵管が詰まってしまうことがあります。
【卵管因子による不妊の主な原因】
- クラミジア感染症
- 子宮内膜症
| 子宮に問題がある(子宮因子) |
子宮の中が、何らかの原因(子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮腺筋症、先天的な形態異常など)で変形していたり、子宮内膜が妊娠に適した状態を維持できないことにより、着床しにくいことから起こる不妊を「子宮因子」の不妊といいます。
【子宮因子による不妊の主な原因】
- 子宮筋腫
- 子宮内膜ポリープ
- 子宮腺筋症
- 子宮奇形
| 子宮頸管に問題がある(頸管因子) |
精子が子宮へ移動する通り道である子宮頸管に炎症や狭窄などの異常がある場合や、精子の通過をサポートする粘液の分泌量が少ないなど、子宮頸管に問題があるために起こる不妊を「頸管因子」の不妊といいます。
【頸管因子による不妊の主な原因】
- 子宮頸管の炎症
- 子宮頸管狭窄症
- 子宮頸管粘膜不全
| 加齢の影響 |
女性は、30歳を過ぎると妊孕(よう)性(妊娠するための力)が低下し始め、35歳を過ぎると、その低下が加速します。加齢による妊孕性の低下は、卵巣で卵子の数と質が低下すること、子宮筋腫や子宮内膜症などの病気が増えることが主な原因と考えられています。
| 男性因子 |
| 精子を製造する能力に問題がある(造精機能障害) |
精子をつくる働きに障害があり、精子の数が少ない(乏精子症)、またはない(無精子症)、精子の運動性が低い(精子無能力症)といった場合を、「造精機能障害」といいます。
【造精機能障害の主な原因】
- 精索静脈瘤
- クラインフェルター症候群
- 停留精巣
| 精子の輸送路に問題がある(精路通過障害) |
精巣で精子が造られていても、精子の輸送路(精路)がふさがっていなり、狭かったりすることで精子が先へ進めない場合を、「精路通過障害」といいます。
【精路通過障害の主な原因】
- 精巣上体炎、精管炎(クラミジア感染症)
- 逆行性射精
| 副性器(精巣上体、前立腺、精嚢(のう))に問題がある(副性器障害) |
副性器(精巣上体、前立腺、精嚢(のう))に何らかのトラブルがあり、精子の運動能力が低い場合を、「副性器機能障害」といいます。
【副性器機能障害の主な原因】
- 精嚢(のう)炎
- 前立腺炎
| 勃起や射精ができない(性機能障害) |
精巣で精子が十分つくられており、精子の輸送路もふさがっていないが、勃起(勃起障害)や射精(射精障害)などの性機能に問題があり、性交ができない場合を「性機能障害」といいます。性機能障害には、性交ができても膣内で射精できない膣内射精障害や、勃起ができない勃起障害などがあります。
【性機能障害の主な原因】
- 動脈硬化、高血圧、糖尿病、喫煙、飲酒
- 緊張、ストレス、不安
- 不適切なマスターベーション
| 加齢の影響 |
加齢による妊孕(よう)率の低下は、女性に比べて緩やかですが、男性でも起こります。35歳を過ぎると精子の質が徐々に低下すると言われています。精巣の大きさも加齢により徐々に小さくなり、男性ホルモンを作る力も低下していきます。
| その他 |
何らかの免疫異常で、精子に対する抗体(抗精子抗体)が体内に生じることにより起こる不妊を「免疫因子」の不妊といいます。
女性の場合、子宮頸管粘膜や卵管内に、抗精子不動化抗体(精子の運動を止める抗体)が生じると、精子の通過が妨げたり、卵子との結合が妨害されたりするため不妊につながります。一方、男性の場合、抗精子不動化抗体や、抗精子凝集抗体(精子同士がくっついて集まる)などにより、精子の運動が妨げられることから、受精が難しくなり不妊につながります。
不育症について
不育症とは
妊娠はするけれども、流産(反復流産、習慣流産)、死産あるいは早期新生児死亡(生後1週間未満の赤ちゃんの死亡)を繰り返し、子どもを持てない場合、「不育症」とよびます。
| 関連用語 | |
| 流産 | 妊娠22週未満の胎児が母体から娩出されること |
| 死産 | 妊娠12週以降の場合の死亡胎児の出産 |
| 習慣流産 | 自然流産を3回以上繰り返した場合(死産・早期新生児死亡は含まない) |
| 反復流産 | 自然流産を2回繰り返した場合 |
| 早期新生児死亡 | 生後1週未満の死 |
※生化学的妊娠:尿や血液の検査で妊娠反応が陽性となった後、超音波で胎嚢(のう)が子宮内に確認される前に、月経様の出血が起こり妊娠が終了すること。日本産婦人科学会の定義によると、生化学的妊娠は流産に含まれないため、生化学的妊娠を繰り返しても、「不育症」に該当しません。
不育症のおもなリスク因子
不育症の主なリスク因子には、カップルの染色体異常の他、女性の子宮形体異常、内分泌異常、凝固異常、母体の高齢年齢などがあります。
| カップルの染色体異常 |
流産を繰り返す場合は、カップルのどちらか一方に染色体構造異常(均衡型転座など)がある可能性が高くなります。転座とは、染色体の2か所が入れ代わることを言います。遺伝子の過不足はないため、その人は健康ですが、卵子や精子が造られる減数分裂の過程で、染色体に過不足が生じることがあり、流産の原因となります。
| 子宮形態異常 |
双角子宮、中隔子宮などの子宮などの子宮の形態異常がある場合には、流産・早産を繰り返すことがあります。子宮の形によっては、着床の障害になったり、胎児や胎盤を圧迫して、流産・死産になることがあると考えられています。
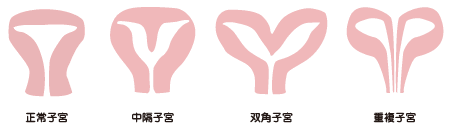
※子宮形態異常(出典「反復・習慣流産(いわゆる「不育症」)の相談対応マニュアル」)
| 内分泌異常 |
甲状腺機能亢(こう)進症、甲状腺機能低下症、糖尿病などでは、流産のリスクが高くなります。甲状腺自己抗体の影響などや、高血糖による胎児染色体異常の増加の関与が指摘されています。なお、これらの内分泌疾患では、早産等の産科合併症のリスクも高いため、妊娠前から妊娠中にかけて良好な状態を維持することが重要です。
| 用語説明 | |
| 甲状腺亢進症 | 甲状腺が活発に活動し、血中に甲状腺ホルモンが過剰分泌(亢進)される病気。 代表的なものに、バセドウ病やグレーブス病があります。 |
| 甲状腺低下症 | 甲状腺ホルモンの分泌量が減り、新陳代謝が低下する病気を甲状腺機能低下症といいます。 |
| 凝固異常 |
血液の凝固を助け、出血を止めるために必要なたんぱく質(凝固因子)に異常があると、血栓が造られやすくなり、流産や死産を繰り返すことがあります。
抗リン脂質抗体症候群、プロテインS欠乏症、プロテインC欠乏症、第Ⅻ因子欠乏症などの一部では、血栓症などにより、流産・死産を繰り返すことがあります。また、流産・死産とならなくても、胎児の発育異常や胎盤の異常をきたすことがあります。
| 用語説明 | |
| 抗リン脂質抗体 | 血中に抗リン脂質抗体と呼ばれる自己抗体が存在することから、動脈や静脈の血が固まる血栓症や、習慣流産などの妊娠合併症をきたす自己免疫疾患。 |
| プロテインS欠乏症、プロテインC欠乏症 | 血液の凝固を活性化させる因子(活性化Va因子、活性化Ⅷa因子)を不活性化させ、血液凝固を防ぐ働きをしているプロテインSやプロテインCが欠乏することにより、血液凝固が起きやすくなり、 血液中に血栓や寒栓が生じやすくなる。 |
| 第Ⅻ因子欠乏症 | 第Ⅻ因子は、血液凝固因子の一つで、欠乏すると血栓や流産を引き起こしやすいといわれいる。ただし、第Ⅻ因子を完全に欠損する場合でも流産しないことがあり、第Ⅻ因子欠乏症と流産の関係については、不明な点も多いのが現状。 |
| その他(リスク因子が特定できない場合) |
一般的な原因検索の検査を行ってもリスク因子が特定できない場合には、流産を生じやすい特別な原因が存在しているのにも関わらず、それが検査で確認できないということではなく、これまでの流産が胎児染色体異常をくり返しである場合が多いと考えられます。この場合には、治療を行わなくともその後の妊娠で出産に至る確率が高いです。これまでの流産や検査結果について十分な説明を受けた後、次回妊娠への不安を少なくしてから妊娠に臨みましょう。
ただし、これまでに経験した流産の回数が極端に多い(5 回以上など)カップルで、かつリスク因子が特定できない場合には、難治性の不育症である可能性があります。
(参考サイト)